Amazon Musicが9月に不具合を起こし、ULTRA HD曲の一部が再生不可になってしまい、問い合わせたがPCのせいにされたりたらい回しにされたりと解決しなかったのでこれを機にApple Musicを導入した。
Amazon Musicの不具合はデスクトップアプリでULTRA HD表示曲をCDスペック以上の出力設定(16bit/44.1kHz以下の設定ならHD再生できる)で再生しようとすると発動する、というものだったが、米津玄師の新曲や藤井風の新作アルバムなど再生数の多い作品でも発生したために徐々に被害者が増加。Amazon側も不具合を認めて対処したようで2週間くらい経過してから不具合が解消された。
Apple Musicは2021年にロスレス対応、プレビュー版を経て2024年から正式にWindows版の提供を開始。しかし排他機能は搭載しなかったため、導入を見送っていたんだけどまあ排他無くてもそんなに音の違いは分からないというのと、排他が無いと当然PCから何か他の音が鳴ると混ざるというのがあるけど、再生中鳴らさなければいいだけなのでそこまで気にするところではないのかもしれない。
実際に導入して見て分かった事が色々あった。
Appleだけハイレゾの定義が違う
AmazonはSD(ロッシーいわゆる圧縮)、HD(16bit/44.1kHzいわゆるCD相当まで)、ULTRA HD(CDより上、24bit/48kHzが多めで24bit/96kHzもある)。ハイレゾの定義は16bit/44.1kHzをどちらかが上回っている事という一般的な基準を使用していてmoraも同様。
Appleは無表記(ロッシーいわゆる圧縮)、ロスレス、ハイレゾロスレスという表記になるんだけど、ロスレスの定義が24bit/48kHzまでなのでmoraやAmazonでハイレゾ扱いでもAppleではハイレゾ扱いにならないという独自基準がある。Appleでは24bit/96kHzまでいかないとハイレゾ扱いにならないのだ。J-POPのハイレゾは24bit/48kHzがけっこう多いので、結果的に他と比べてAppleはハイレゾが少ないなぁ…という感覚になるが、これは24bit/48kHzをハイレゾにしていないせいである事が分かった。
何故Appleだけ歩調を合わせず独自基準なのかというとどうやらiPhoneがDACを使わずに単体で出力可能なのが24bit/48kHzまでらしく、iPhone単独で出力できるのがロスレス、DACを介さないと出力できないのがハイレゾロスレスと線引きしているという事のようだ。
Appleは同一アーティストで圧縮のまま取り残されているのが散見される
意外だったのがB’z作品のほとんどが圧縮音源のままだった。ロスレスになっているのは直近作と最初期のアルバム、あといくつかといったところ。わざとやっているのか、対応が間に合っていないのかは不明だが、先ごろ開始したSpotifyのロスレス配信ではAppleで圧縮のままのB’z作品がロスレスになっているという歓喜の報告がXで相次いでいた事からB’z最強のサブスクはSpotifyが一挙逆転したっぽい。Appleは対応が間に合ってないのか?
B’zがサブスク解禁した1ヶ月後にAppleがロスレス配信開始を発表しているので、B’zのサブスクは1度全部圧縮で解禁されているわけで、その辺りで滞りがあったのかもしれない。
ただ不思議なのは大黒摩季のアルバムリマスターシリーズでは『永遠の夢に向かって』だけが謎にロスレスマークが無く圧縮で配信されている。意図があるとは思えないのでこのような配信グレードのミスは多そうだ。
一方でAmazonでは既にほとんどないSD配信しか許可していないMr.ChildrenはAppleでは普通にロスレス配信していた。
またAmazonで散見される同じ曲がアルバムバージョンに差し替え統一されてしまう不具合はAppleでは発生していなかった。AmazonではULTRA HDが優先される仕様になっているようで、内部でしっかりとしたタグ付けがされていない同一タイトル曲で本来そのアルバムはHD音源でもULTRA HDがあればそっちを引っ張ってきてしまうという特性があるようで、この際にシングルバージョンをアルバムバージョンに置き換えてしまう事例が時々発生する。米米CLUB「Special Love」もこの被害に遭っている曲の1つでAmazonで配信されている「Special Love」はシングルもベストアルバムも全てアルバムバージョンに差し変わってしまっている。Appleではこのような現象は発生せず「Special Love」はちゃんとオリジナルアルバム以外はシングルバージョンになっていた。初期ビートルズのモノラルのはずのアルバムの音源が2023年のデミックスでステレオ化された音源に勝手に差し変わっていたなんてことも…。
こういった点においてAmazonではそれが本当にそのアルバムに入っている正規の音源なのか不正確で信用できないところがある。HDとULTRA HDが混在しているベストアルバムなんかはかなり怪しく他のアルバムの音源が混在している可能性が高そうだ。音源の正確性ではAppleの方が確かだろう。
音の違い
Amazonは音がしっかりしているというか低音が効いている感じがする。Appleは少し軽めの音でクリアな感じがする。同じ条件の曲でAmazonの方を排他なしで整えてもこの傾向は変わらない(逆に言えばAmazonで排他ONにしてもあまり違いが…)。FLACとALACの違いなのか、Apple Digital Mastersとやらで生じる差なのかは不明。
WALKMAN NW A-306でのアプリの挙動は比べるまでもない
Apple圧勝。
ストリーミング対応ウォークマンとしてアンドロイド搭載になって2代目となるAシリーズのA300系ウォークマンだが、大前提で大欠陥がユーザーに報告されており、Wi-Fi接続して有線接続で聞いていると左から小さなジリジリ音が終始鳴り続けるという不具合があって発売から2年経過しても修正対応不可能となっている(気づかない人は気づかないらしいが、レビュー等で指摘しているユーザーも少なくない)。
これを抜きにしても音質重視で10年近く前のスマホのスペックのようなかなりの低スペックとなっているため、Amazon Musicアプリは重すぎてまともに稼働しない。作品をクリックしても読み込んだままグルグルしているだけで表示されないのがデフォだし、ようやく曲目が出てきてダウンロードしようにもなかなか動かない。ダウンロード途中でも表示が止まるのでダウンロードが不完全だったなんてことも…。
試しにスマートフォンAQUOS sense8でAmazon Musicアプリを動かしてみたらサクサク動いたので、Amazon Musicは基本的に現代のスマホのスペックに合わせたものにはなっているようだが、前時代の低スペックは考慮していないらしい。
対してApple Musicは低スペックのストリーミングウォークマンでもサクサクと動く。デスクトップアプリ同士だとむしろAmazonの方が動きが若干早いんじゃないかというくらいだったが、モバイル版アプリでこんなに大差があったとは。
CD購入しないサブスクオンリー視聴のアルバムやシングルなんかは、PC→HE99で聞く前に1回車で移動中に聞くためにA-306でダウンロードしてオフライン再生という聞き方もしていたんだけど、前述のようにAmazonが重すぎるのでそれを断念する事も多く、少し不便に感じていた。Appleではこの聞き方はかなり捗りそうだ。
WALKMAN NW-A300におけるDolby Atmos対応について
Amazon Music→対応
Apple Music→非対応
ここはハッキリと別れた。Appleの場合はAndroidスマホでも対応と非対応があるようだが基本はApple製品で最適化している感じ。NW-A300のAndroidは14までアップデートされたがAmazon Musicアプリがまともに動かないくらい低スペックなのでまあ無理なのだろう。非対応の場合は設定項目がそもそも存在しない。
PC(デスクトップ版アプリ)ではこれが逆でAmazon Music非対応、Apple Music対応となる。
とりあえずしばらく併用しようかなとは思うんだけど、年額料金<ライブ1回でかかる費用なのを考えればライブ2回分でお釣りがくる。もうライブに行くことはないと思うので、AmazonとAppleを併用したところで出費はライブに年数回行っていた2018年以前よりも抑えられるだろう。
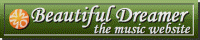
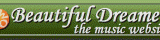

コメント